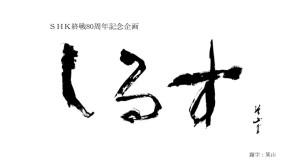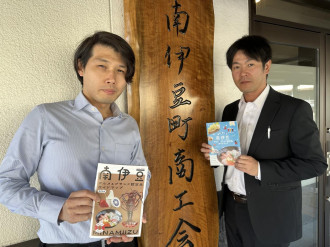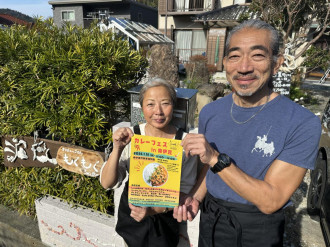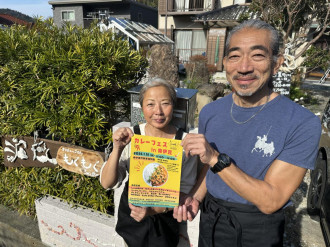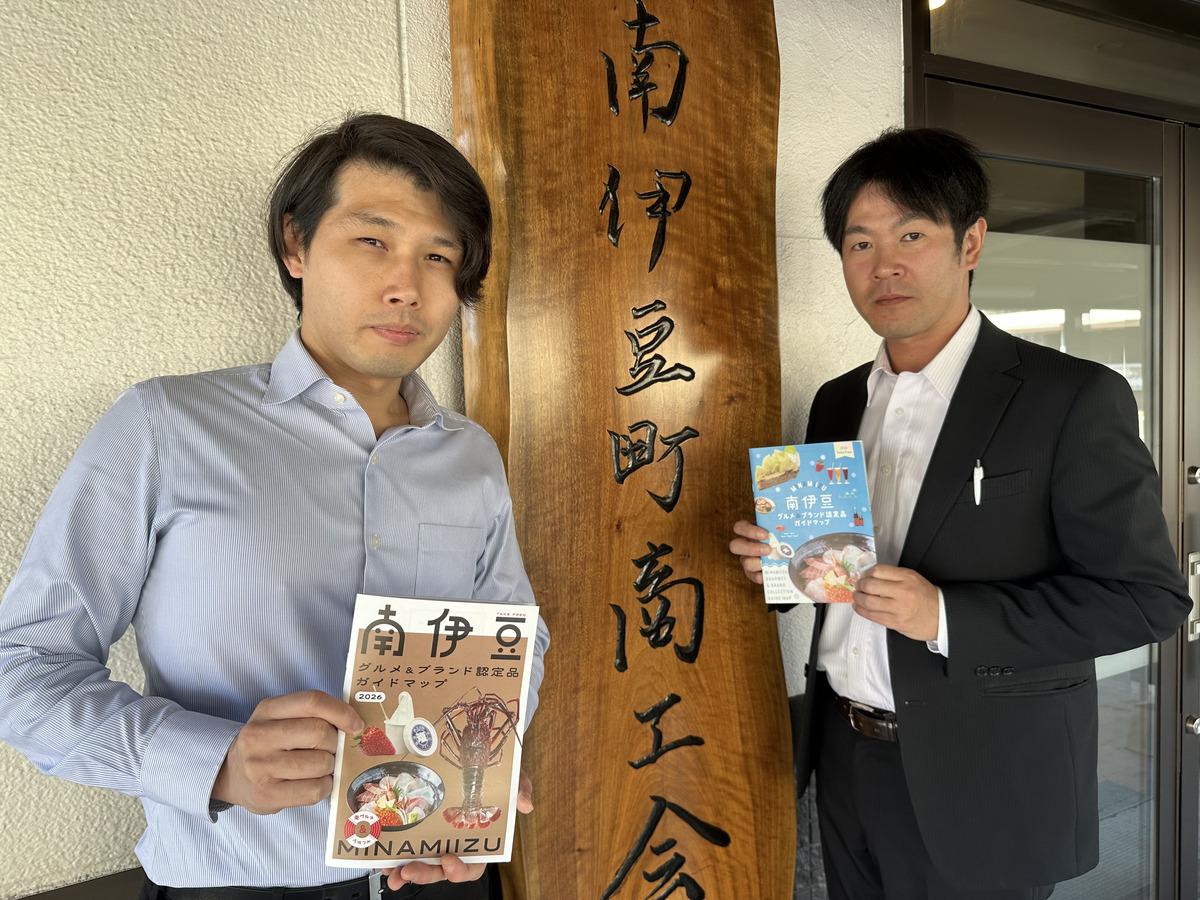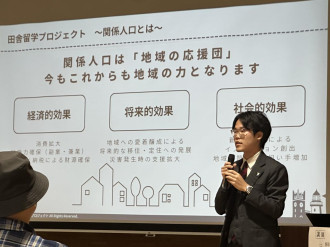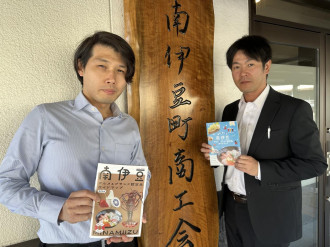南伊豆町で「小稲の虎舞」奉納 江戸時代が起源の県指定無形民俗文化財

静岡県指定無形民俗文化財にも指定されている「小稲の虎舞(こいなのとらまい)」が10月5日、南伊豆町小稲の浜辺で奉納された。地域の小稲来宮会(こいなきのみやかい)が中心となって毎年守り伝えているもので、地元住民や観光客など多くの見物客が浜を訪れた。
虎舞の起源は江戸時代にさかのぼると伝わる。中国・明の英雄、鄭成功(ていせいこう)を題材にした歌舞伎「国性爺合戦(こくせんやかっせん)」が流行した際、その劇中に登場する虎退治の場面を基に舞が生まれたとされる。当時、海運や交易を通じて異国文化の影響を受けた伊豆の人々が、物語を自らの信仰や生活に結びつけ、独自の舞として発展させたという。
この日は15時ごろ、地区の集会所に集まった若衆約20人が「虎の御神酒(おみき)」を行い、太鼓と笛を鳴らしながら町内の巡行を開始した。夕暮れ時、浜辺に設けられた奉納舞台に到着すると、いよいよ虎舞が始まった。太鼓と笛の音が一段と高らかに響く中、2人一組の舞手が息を合わせて虎を操って舞台上で勢いよく跳ね上がり、後ろ足を高く掲げたり、牙をむいて海に向かってほえたりした。
最大の見せ場は、武将・和藤内(わとうない)が虎と闘い、生け捕りにする場面。観客からは「頑張れ虎!」と声援が上がり、舞が終わると拍手と歓声が響いた。
現在は五穀豊穣や大漁、地域の安寧を祈る儀式として、来宮神社(南伊豆町手石)の例祭に合わせて奉納されており、地元の子どもたちも太鼓や笛に加わり、世代を超えた継承の輪が広がりつつある。小稲来宮会の土屋文男会長は「若衆が少ないため、近隣の手石地区の有志にも協力してもらっている。祭りの担い手は減っているが、この伝統行事は後世に引き継いでいきたい」と意欲を見せる。