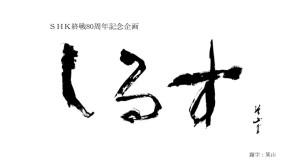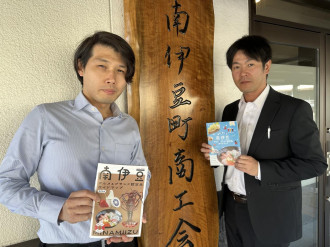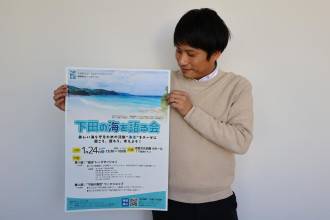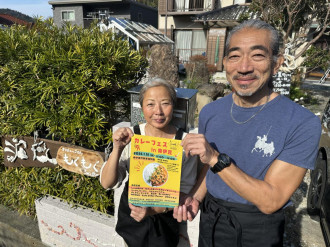【伊豆下田ローカル発見隊 Vol.1】SHK終戦80周年企画番組「昭和20年下田空襲」

「伊豆下田ローカル発見隊」は、地域の「知る人ぞ知る物語や魅力」を探し出し、広く伝えていく特集です。
1回目の今回は、下田有線テレビ放送(SHK)が終戦80周年企画「しるす」の一環で制作した自主制作番組『昭和20年下田空襲 ~あの日、下田で何が起きていたのか~』を紹介します。
下田有線テレビ放送(SHK)とは?

1970(昭和45)年に設立された、静岡県下田市に本社を置く地域密着型のケーブルテレビ局です。
四方を山と海に囲まれ、テレビ電波が一般家庭で受信しにくい下田市内に向けて、地上デジタル放送の同時再放送を行っているほか、日々の取材を基にした地域ニュースなどの自主制作番組も手がけています。
電波が届きにくい下田市内で安定したテレビ視聴を支える存在であり、地元情報をタイムリーに届け、地域コミュニティーをつなぐ役割を果たしています。
SHK終戦80周年企画「しるす」

終戦80年の節目となる2025年、SHKでは「しるす」と題した記念企画を立ち上げ、いくつかの自主制作番組の配信と、市内に残る戦争の爪痕を取り上げたニュース発信を年間を通じて行っています。
企画のきっかけは、同社のカメラマン・淺田力さんの発案でした。地域ニュースの取材で市内各地を訪れる中、多くの慰霊碑や鎮魂碑が残されていることに気付いた淺田さんは、調査を進める中で終戦間際の下田に何度も空襲があった事実を知りました。
「移住者という立場ではあるが、この現実と体験を後世に伝えるべきだと感じた。テレビカメラを持つ自分だからこそ、体験者本人の声を映像で残せると考え企画を提案した」と淺田さんは振り返ります。

【番組紹介】昭和20年下田空襲 ~あの日、下田で何が起きていたのか~

下田にも戦争が来た日~空襲が始まった昭和20年春
1945(昭和20)年4月12日、静岡県下田市。戦争末期、日本本土への空襲が本格化する中、米軍の大型爆撃機B29が下田の空に飛来しました。それまでうわさに聞く程度だった戦争の影響が、突如として人々の日常に押し寄せた瞬間でした。
当時、国民学校を卒業した子どもたちは、現在の下田高校の場所にあった県立豆陽(とうよう)中学校や、現在の下田メディカルセンターの場所にあった県立下田高等女学校に進学していました。
原町出身で中学校2年生だった太田真康さんは、その日の朝を、こう振り返ります。

町の方を見ると、すでに煙が立ち上っていた。原町、中原町、池之町の辺りに爆弾が落とされたと知り、慌てて友人たちと逃げた。
橋の近くまで来ると、火の手が上がっていて、煙で先が見えなかった。どこへ行けばいいか分からず、ただ走った。
1年後輩の土屋勇さんも、同じように空襲の衝撃を体験しました。

家に帰ってみると、中原町の半分が焦土と化していた。なじみのある通りや店が焼け落ち、呆然と立ち尽くした。
特に川沿いの辺りはひどく、軍隊が整列していた場所が狙われたと聞いた。
「爆風の向こうに消えた声」──失われた命と向き合って
空襲は物理的な被害だけでなく、人々の心にも深い傷を残しました。何気ない日常が一瞬にして奪われ、親しい人との別れは突然訪れました。
土屋さんの記憶に最も強く残っているのは、姉・ともゑさんの死です。

病院へ運んだが、空襲が続いていたためすぐには診てもらえず、出血多量で亡くなった。
ともゑの死は、初めて“戦争が人を殺す”という現実を突き付けられた出来事だった。
ともゑさんと同級生だった土屋さんの妻・とく子さんは、亡くなった翌日に学校でともゑさんの死を聞かされました。ともゑさんの間際の様子は、結婚後に義姉から聞いたといいます。

太田さんも、8月1日の空襲で姉を失いました。グラマン戦闘機による機銃掃射が原因でした。

遺体は腐敗が進んでいたこともあり、見つかったときには誰もが衝撃を受けた。
あのときの気持ちは、言葉では言い表せない。
命を奪うだけでなく、記憶に深い傷跡を残す。空襲とはそうしたものでした。
「終戦の日、そして再び歩き出した町」--戦後の暮らしと復興の記憶
1945(昭和20)年8月15日。玉音放送によって、日本の敗戦が国民に知らされました。徳子さんの近くの家にラジオがあり、近所の人々や兵隊たちが座敷いっぱいに集まっていました。

私たち子どもたちにとっては「あぁ、戦争がもう終わった。これで空襲はもうない」というくらいの気持ちだった。兵隊さんたちとは、だいぶ気持ちが違ったのではないか。
だが、戦争が終わったからといって、すぐに平穏な生活が戻ったわけではありませんでした。
白米はなかなか食べられず、町の子は豆かすや芋を混ぜたご飯を食べて飢えをしのいでいたと言います。勉強どころではなく、毎日を生き延びるだけで精いっぱい。学校でもしばらくの間、まともに授業は行われませんでした。

そんな中でも、町は少しずつ復興していきました。1940(昭和15)年を最後に中止されていた下田太鼓祭りが、1946(昭和21)年、幼稚園のグラウンドで再開されました。
学校も再編され、1948(昭和23)年には東洋中学校が下田第一高校に、下田高等女学校が下田第二高校に改称。翌年には下田北・南高校となり、やがて現在の下田高校へと統合された。その頃になって、ようやく復興の手応えが感じられるようになったと言います。
戦争の終わりは、新たな日常の始まりでもありました。しかし、その過程には数え切れないほどの苦難と葛藤がありました。
語り手たちは、それぞれの立場で「あの日々」を生き抜き、今こうして語ってくれています。
──私たちは、こうした声に耳を傾け、記録し、次の世代へと語り継がなければなりません。