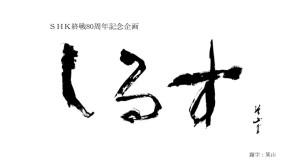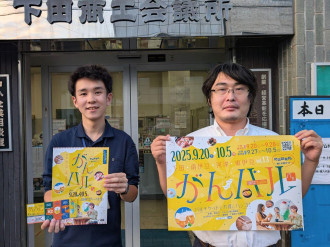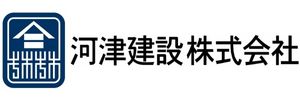伊豆最古の宮・白浜神社の例大祭 伊豆諸島の議員も参列し新たな交流の絆

2400年の歴史を持つとされ、近年は海岸に建つ真紅の鳥居が海外旅行客からも人気を集めている伊豆最古の宮・白浜神社(下田市白浜)における最大の祭典「白浜神社例大祭」が10月28日~30日に行われた。
伊豆諸島に向けてかがり火をたき、宮司が祝詞を奏上する(関連画像15枚)
下田・白浜地区で千年以上続く伝統祭。白浜神社の祭神は女神である伊古奈比咩命(いこなひめのみこと)と、現在は三島大社の主神であり、商業と漁業の男神である三島大明神(別名・恵比寿さん)。敷地内に祠(ほこら)が設けられている見目(みめ)弁財天が二神の仲を取り持ったとされ、同神社は夫婦和合・縁結びにご利益があるパワースポットとしても知られている。
初日の28日夜には「火達祭(ひたちさい)」が行われた。太古の昔に三島大明神が作ったとされる伊豆諸島に向けてかがり火をたき、島々の神に祭典の開始を合図する神事。白浜地区の伝統として受け継がれる豆州白浜太鼓の奉納やリズムに合わせた打ち上げ花火も華やかに行われ、見学者からは感嘆の声が漏れた。
近年は三島大明神の后神と子息たちがそれぞれ住んだと神話の中でいわれる伊豆諸島からも来賓があり、今年は神津島や新島から村議会議員ら4人が祭典に参加。白浜太鼓や花火を楽しんだ後、直会(なおらい)と呼ばれる酒宴で白浜神社関係者らと再会を喜び合い、親睦を深めた。新島村議会議長を務める木村諭史さんは「伊豆半島の東側を回ると、火山を通じた半島と離島のつながりが感じられる」と話し、「観光はもちろん、経済の面でも下田と島々の交流を深めていければ」と今後への期待を語った。
中日の29日早朝には、下田市無形文化財第1号に指定される「三番叟(さんばそう)」が奉納された。昨年から再開された三番叟だが、演者である3人のうち2人は新人で、練習にも苦労したという。同神社の氏子総代を務める藤井英次さんは「三番叟奉納をはじめ、祭典の存続には年々困難を感じている。エリアの垣根を越え、市内全体で祭典に参加・協力できる体制ができれば」と話す。
最終日である30日には、祭典が無事完遂されたことを再び伊豆諸島の神々に知らせるため、青竹に和紙を付けた御幣(おんべ)を海に流す「御幣流祭(おんべながしさい)」が執り行われた。例年通り、海岸鳥居から海面に向けて、人の背丈ほどある御幣を宮司が次々に投げ入れ納めたが、今年は強風のため所作にも苦労が見られた。通例は午後から夕方にかけて行われる神事だが、今年は潮の流れの関係で午前9時から行い、異例の時間帯となったために見学者は少なめとなった。
祭典期間中、神社を中心にみこしと太鼓台が白浜地区を練り歩き、子どもみこしも元気に巡行した。3日間とも天候に恵まれ、神社の駐車場には恒例となった屋台やキッチンカーが立ち並び、訪れた人々を楽しませ、交流の場になっていた。30日夜にはみこしが神社に戻る「宮入り」の儀式が行われ、無事にみこしが収められると参加者全員が三三九度で祭典が無事に終了したことを祝った。