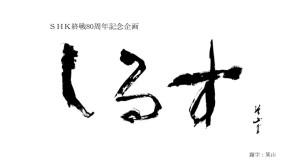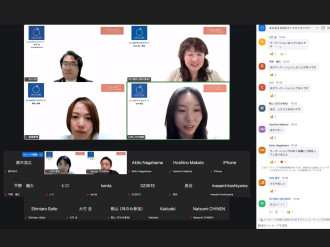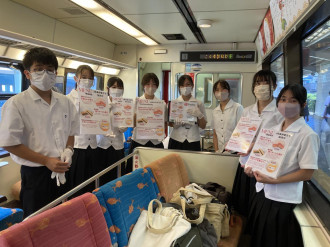6年ぶりに「麦わら舟流し」 河津・見高浜で先祖供養の伝統行事

河津町の見高浜で8月16日、お盆の伝統行事「麦わら舟流し」が行われた。コロナ禍や台風による荒天で中止が続き、6年ぶりの開催を地元住民らが見守った。
河津町の寺院では毎年8月16日に施餓鬼(せがき)法要が営まれる。見高地区の真乗寺では特に「浜施餓鬼」と呼ばれる法会(ほうえ)が行われ、新盆から3年までの檀家が故人をしのぶ。この法会の後、地元の男性らが麦わらで作った精霊船を海へ流し、先祖の魂を供養するのが古くからの習わしとなっている。
真乗寺は1539年に創建された臨済宗建長寺派の寺院。本堂の天井一面には、2匹の竜と河津桜が色彩豊かに描かれており、見高地区の菩提(ぼだい)寺として知られている。
当日は8時30分から檀家の男性らが集まって精霊船作りを始めた。「ハチコ」と呼ばれる材木を芯に、麦わらの太い束をいかだのように組んで船底を形作り、側面は麦の束を竹ひごで締めて編み上げる。背面は同様に編んだパーツを取り付けた。船にはそれぞれ櫓(ろ)とかじを持った船頭とこぎ手に加え、死者が寂しくないようにと三味線を持った芸者の計3体の人形も載せる。すだれの屋根を付けた後は数十本の五色旗で鮮やかに飾り付け、後方にはちょうちんと吹き流しの付いた2本の長いさおを刺して15時ごろに完成した。作業を終えた人たちは「6年ぶりでちょっと心配だったが、やれば何とか形になるもの」とほっとした様子を見せた。
かつては川を挟んで川東・川西の両地区が1隻ずつ、その出来映えを競うように製作していたというが、担い手の減少により今回は1隻のみとなった。
16時からの浜施餓鬼は10組ほどの家族が参列し、真乗寺の住職を含む5人の僧侶が読経をするなど、厳かに執り行われた。その後、麦わら舟は漁港の船着き場に移され、男性8人ほどが支えながら港内を時計回りに3周させて一連の法要を締めくくった。
今年初めて舟作りに参加した20代の桑原輝(あきら)さんは「麦わらを竹ひごで締めるのが難しかった。伝統ある行事なので僕たちが後世に引き継いでいきたい」と決意を新たにする。